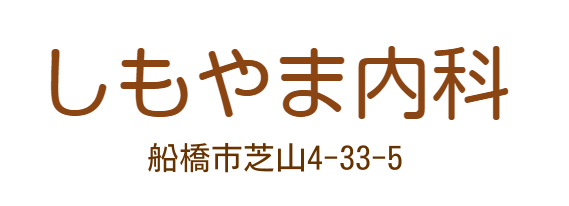このページの要点(SGLT2阻害薬×DPP-4阻害薬 併用)
- DPP-4+SGLT2の併用は「低血糖が起こりにくい」組み合わせで、食後高血糖と空腹時高血糖を分担できます。
- 一方で脱水・尿路/性器感染・(特に1型では)ケトアシドーシスに注意が必要です。
- 発熱・嘔吐・下痢・絶食・手術前後は、一時休薬が必要になることがあります(自己判断せず主治医へ)。
「dpp4 sglt2 併用」「sglt2 dpp4 合剤」「使い分け」で調べている方へ。
このページでは、DPP-4阻害薬+SGLT2阻害薬の併用が向くケースと、注意すべき副作用・休薬(シックデイ)目安を、実践的にまとめます。
SGLT2阻害薬+DPP-4阻害薬は「何を改善する併用」?
併用の狙い(ざっくり)※薬剤名は例。実際は年齢・腎機能・合併症などで個別に判断します。
| 食後高血糖 | DPP-4阻害薬が得意(インクレチンを介して食後の血糖上昇を抑える) |
|---|---|
| 空腹時高血糖 | SGLT2阻害薬が得意(尿中へ糖を排泄し、24時間の血糖を底上げしやすい) |
| 低血糖 | どちらも単独では起こりにくい(ただしSU薬・インスリン併用では低血糖に注意) |
| 体重 | SGLT2阻害薬は体重減少方向に働きやすい(過食の“言い訳”にならないよう注意) |
「合剤(1錠にまとまった薬)」はある?(代表例)
日本で使われる代表的なDPP-4+SGLT2配合剤(合剤)の例です。
- カナリア配合錠(テネリグリプチン+カナグリフロジン)
- トラディアンス配合錠(エンパグリフロジン+リナグリプチン)
①飲み忘れが減る ②処方が整理しやすい ③通院負担が減ることがある
合剤の注意
片方だけ中止したいときに調整しづらい(副作用・脱水時などは特に)
併用が「向く」ケース(目安)
- 食後高血糖が残り、DPP-4単剤では物足りない
- 空腹時高血糖が高めで、日内変動をならしたい
- 体重・血圧・心腎リスクも含めて総合的に管理したい(個別評価が前提)
- 低血糖をできるだけ避けたい(ただし他剤併用次第)
併用で注意するポイント(ここが一番大事)
1) 脱水(夏・発熱・下痢・嘔吐・食事が取れない時)
SGLT2阻害薬は尿量が増えやすく、脱水・血圧低下・ふらつきにつながることがあります。
特に高齢・利尿薬内服・暑い環境・水分摂取が少ない方は要注意です。
2) 尿路感染・性器感染(かゆみ・痛み・頻尿・発熱)
尿中の糖が増えるため、膀胱炎・外陰部の症状が出やすいことがあります。症状があれば早めに相談してください。
3) ケトアシドーシス(特に1型糖尿病/極端な糖質制限/絶食)
強い体調不良・嘔吐・腹痛・息苦しさ・強い倦怠感などがあれば、“血糖が高くなくても”緊急評価が必要になることがあります。
とくに1型糖尿病でSGLT2阻害薬を使う場合は、主治医の管理下で慎重に行います。
発熱・嘔吐・下痢・食事が取れない・脱水が疑われる・手術/検査で絶食…
→ 自己判断で続けず、まず主治医に連絡(夜間/休日は救急受診が必要なこともあります)
よくある質問(FAQ)
Q. DPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬は、併用しても大丈夫ですか?
多くのケースで併用される組み合わせです。低血糖は起こりにくい一方、脱水・尿路感染・(状況によっては)ケトアシドーシスなどの注意点があります。年齢、腎機能、他剤併用で安全性が変わるため、主治医と一緒に判断します。
Q. 低血糖は起こりますか?
DPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬だけなら低血糖は起こりにくいです。ただし、SU薬やインスリンを一緒に使う場合は低血糖リスクが上がるため、用量調整が必要になることがあります。
Q. トイレが近くなるのが心配です。
尿量が増えることがあります。血糖が高いほど尿糖が増えやすく、開始直後は特にトイレが近く感じることがあります。脱水にならない範囲で水分を確保し、強い口渇・ふらつきがあれば相談してください。
Q. 膀胱炎(尿路感染)が起きやすいって本当?
尿路感染・性器感染のリスクが上がることがあります。排尿痛、頻尿、発熱、外陰部のかゆみ等があれば早めに受診してください。
Q. 腎機能(eGFR)が低いと使えませんか?
SGLT2阻害薬は腎機能により血糖降下作用が弱くなる場合があり、適応・用量・継続可否は腎機能で変わります。開始前後に採血で確認しながら調整します。
Q. 風邪で食事が取れない時は飲み続けていい?
脱水やケトアシドーシスのリスクが上がる状況では一時休薬が必要になることがあります。自己判断せず、主治医へ連絡してください(夜間・休日は救急受診が必要なこともあります)。
Q. 合剤と別々の錠剤、どちらが良い?
飲み忘れ対策なら合剤が有利です。一方で、片方だけ中止・減量したい場面(副作用、脱水時など)では別錠のほうが調整しやすいことがあります。
👨⚕️ この記事の監修医師
しもやま内科 院長
日本内科学会 総合内科専門医
日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医
日本循環器学会 循環器専門医
日本老年医学会 老年病専門医・指導医
日本甲状腺学会 甲状腺専門医
糖尿病の薬物療法(SGLT2阻害薬・DPP-4阻害薬を含む)を、年齢・腎機能・合併症まで踏まえて個別に最適化しています。
服薬の組み合わせに不安がある方、体調不良時の対応(休薬の目安)を整理したい方はご相談ください。