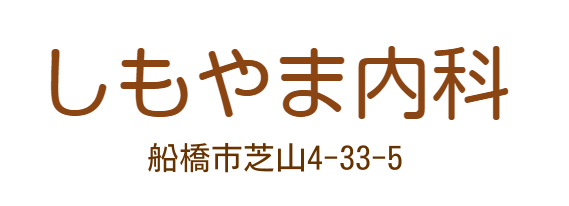🔊 このページの要点(糖尿病教室⑤)
糖尿病の合併症は、腎(DKD)・心血管・網膜・神経・足に起こりやすく、自覚症状がないまま進行することがあります。
HbA1cは重要ですが平均値の指標のため、低血糖や血糖変動も含めて安全に評価する考え方(beyond HbA1c)も大切です。
早期の検査と継続管理で、将来のリスクを下げることができます。
▶ HbA1cだけでは見えない評価軸:/dm/beyond_hba1c/
- 腎(DKD):糖尿病性腎臓病(DKD)総合ガイド
- 心血管:心筋梗塞・脳梗塞・心不全・末梢動脈疾患(足の血流)など
- 網膜:糖尿病網膜症(眼底検査で早期発見)
- 神経:糖尿病神経障害(しびれ・痛み・自律神経症状)
- 足:足病変(傷・感染・壊疽)とフットケア
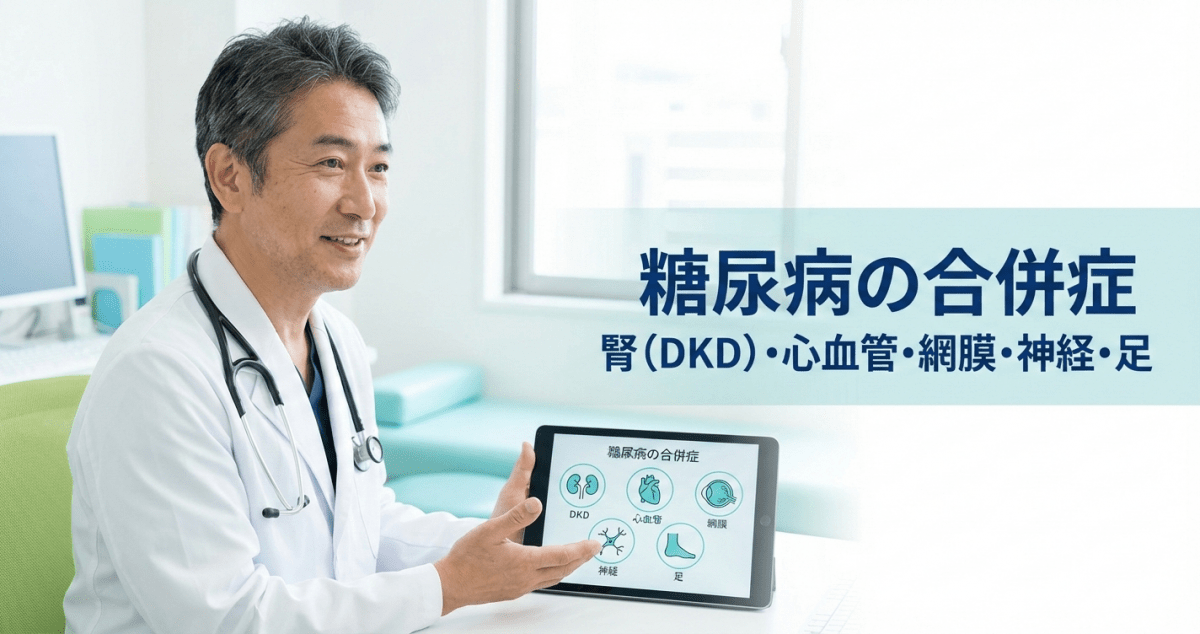
糖尿病の合併症はこんなに怖い
「将来失明するのでは?」「透析になったらどうしよう」「足のしびれが気になる」――糖尿病で不安が大きいのは、合併症が自覚症状がないまま進行し、ある日突然、生活や命に関わる問題として現れることです。
このページでは、糖尿病の合併症が起こりやすい腎(DKD)・心血管(心筋梗塞/脳梗塞)・網膜・神経・足を中心に、「何が起こるのか」「早期に何をチェックすべきか」を整理します。
神経障害(神経・足につながる合併症)
糖尿病神経障害(全体像)
神経障害は「感覚」「運動」「自律神経」の3つに分かれます
| 感覚神経の障害 | しびれ・痛み・感覚低下(足の傷に気づきにくくなる) |
|---|---|
| 運動神経の障害 | 筋力低下・歩きにくさなど(進行すると転倒リスク) |
| 自律神経の障害 | 便秘・下痢、立ちくらみ、発汗異常、排尿トラブル、性機能低下など |
糖尿病の神経障害は、障害を受ける神経の種類によって以下のように分かれます。
感覚神経の障害:感覚・知覚をつかさどる神経の障害です。
運動神経の障害:全身の運動をつかさどる神経の障害です。
自律神経の障害:多種多様な仕事をしている、自律神経の障害です。
感覚神経の障害
感覚、知覚の障害では、手先、足先がピリピリ痺れる、ジンジンする。
足に針で刺されるような痛みがあり、夜眠れない。
足の裏が皮をかぶったように感じる。
痛みを感じなくなる、触ってもわからない。
こむら返りをよく起こす。
などの症状が生じます。
📝 感覚神経障害のよくある症状
- 足先がピリピリ・ジンジンする(しびれ)
- 針で刺されるような痛みで眠れない
- 足裏が「皮をかぶった」ような感覚
- 痛みや熱さを感じにくい/触ってもわかりにくい
- こむら返りを起こしやすい
※感覚が鈍いと「靴ずれ・やけど・小さな傷」を見逃し、足病変につながりやすくなります。
自律神経障害
自律神経の障害では、胃腸の調子が悪くなり便秘、下痢などを起こしやすくなります。
立ちくらみがする。汗をかきにくい。残尿がある。性機能低下などが生じます。
いずれも生活の質(QOL)を著しく下げるものです。また、厄介なことに一度そうなってしまうと、後から糖尿病治療を強化してもなかなか消えません。
🧩 自律神経障害のポイント
- 便秘・下痢など、胃腸の不調が続く
- 立ちくらみ(起立性低血圧)
- 汗をかきにくい/かきすぎる
- 残尿感・排尿トラブル
- 性機能の低下
一度はっきり出てしまうと、あとから血糖を整えても「症状がゼロに戻る」まで時間がかかることがあります。
だからこそ、早めの血糖・血圧・脂質の総合管理と、症状に応じた対症療法が重要です。
糖尿病神経障害は、起こしてしまうと「元に戻す」良い方法が限られるため、予防として血糖コントロールが重要です。
神経障害があると足のけがに気づきにくく、糖尿病のコントロールが悪いと感染にも弱くなるため、重い感染につながることがあります。
足をよく観察しましょう。傷はないか、魚の目・タコはないか、爪の手入れはできているか、水虫は治療されているかを確認します。これらが感染の原因になります。

足にできた傷を放置しておくと壊疽になることがあります。糖尿病患者さんでは血流も悪く傷の治りが悪いため、治療のために広範囲の切除や切断が必要になることもあります。
糖尿病網膜症(網膜)
糖尿病網膜症を起こすと視力が低下し、最終的には失明することもあります。
目の奥の網膜は非常に大事な部位で、高血糖が続くと細い血管が徐々に詰まってきます。何年もかけて徐々に視力が落ち、しまいには失明することがあります。
糖尿病網膜症を良くするには?
糖尿病網膜症を「悪化させない」ために
血糖だけでなく、眼科連携と総合管理が重要です
| 基本 | 血糖コントロール(HbA1cの改善)+血圧・脂質・禁煙も含めた総合管理 |
|---|---|
| 注意点 | 進行した網膜症がある場合、血糖を急激に下げると悪化することがあるため、眼科と連携して調整 |
| 検査 | 自覚症状がなくても定期的な眼底検査(年1回を目安、所見があれば頻度アップ) |
糖尿病網膜症を予防するには血糖コントロールが重要です。
ただし、既に進行した網膜症がある方で血糖を急激に下げると悪化することがあるため、眼科と連携しながら慎重に調整します。
自覚症状がなくても年に1回は眼科受診(眼底検査)をおすすめします。
腎の合併症:糖尿病性腎臓病(DKD)
従来「糖尿病性腎症」と呼ばれてきた腎の合併症は、現在はより包括的な概念としてDKD(糖尿病性腎臓病)として評価・治療します。
早期には自覚症状が乏しいため、尿中アルブミン(ACR)とeGFRで定期的にチェックし、血糖・血圧・減塩・薬を組み合わせて進行を抑えることが重要です。
▶ DKDの代表ページ:糖尿病性腎臓病(DKD)総合ガイド
(ステージの詳しい説明):糖尿病性腎症のステージ別解説
人工透析を避けるために重要なのは、自覚症状がない早期のうちに検査と治療を続けることです。
心血管の合併症(動脈硬化)
糖尿病患者さんは、狭心症・心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症(足の血流低下)など、動脈硬化性疾患を起こしやすくなります。
血糖だけでなく、血圧、脂質、体重、禁煙など、複数の危険因子を一緒に整えることが重要です。
高血圧症、脂質異常症、肥満(特に内臓肥満)、喫煙、加齢も動脈硬化の危険因子です。
糖尿病だけ頑張っても十分な治療はできません。血糖を下げるだけでなく、血圧コントロール、脂質のコントロールもしっかりすることが重要です。
次のページ:糖尿病教室⑥ 糖尿病治療のまとめ(食事・運動・薬物療法)
前のページ:糖尿病教室④ 糖尿病の合併症(網膜症・腎症・神経障害/心筋梗塞・脳梗塞)は自覚症状なく進行
❓ よくある質問(糖尿病教室⑤)
Q. しびれが出たら、もう元に戻りませんか?
ただし、血糖・血圧・脂質を整え、足のケアや痛みの対症療法を組み合わせることで、悪化を抑えたり、生活の困りごとを軽くできる場合があります。早めに相談してください。
Q. 足に小さな傷があるだけでも受診した方が良いですか?
赤み・腫れ・熱感・痛み・膿がある、傷が大きくなる、黒っぽく見える、発熱がある場合は早めに受診してください。
Q. 眼底検査はどのくらいの頻度で必要ですか?
網膜症は症状がなく進むことがあるため、視力が落ちてからではなく「症状がないうちの検査」が大切です。
Q. HbA1cが良ければ、合併症は心配いりませんか?
合併症予防には、HbA1cだけでなく、低血糖の有無、血糖変動、血圧、脂質、禁煙、腎機能(eGFR/尿アルブミン)などを含めて総合的に管理することが大切です。
Q. DKD(糖尿病性腎臓病)は何でチェックしますか?
早い段階で異常を見つけ、血糖・血圧・減塩・薬物療法を組み合わせることで、進行を抑えられる可能性があります。
Q. 合併症を防ぐために、今日からできることは?
- 血糖・血圧・脂質を「まとめて」整える(総合管理)
- 足を毎日チェック(傷・タコ・水虫・爪)+保湿
- 年1回を目安に眼底検査(必要時は頻度アップ)
- 尿アルブミン・eGFRの定期チェック
- 禁煙・適正体重・継続通院