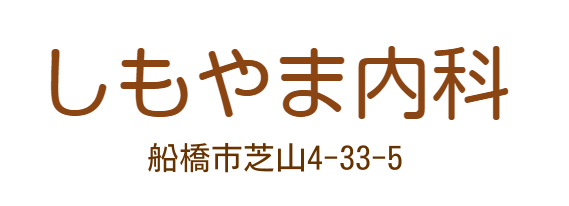従来の慢性心不全治療薬に関しては、慢性心不全に対する薬物療法をご参照ください。そのうえで、この記事をご覧ください。
心不全に対する新規治療薬
近年、新規作用機序をもつ心不全治療薬として、angiotensin receptor/ neprilysin inhibitor (ARNI)、SGLT2阻害薬、hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel (HCN)チャネル阻害薬、可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激薬が相次いで開発され、慢性心不全患者に対する予後改善策が示されました。これらの薬剤は各国の心不全治療ガイドラインでもその使用が推奨されるようになってきています。
ARNI
従来から心不全治療として用いられていたARBと心不全に有効であるネプリライシン阻害薬の配合剤です。
2020年よりサクビトリルバルサルタン(商品名:エンレスト)が保険適応となりました。心不全治療において、標準治療としてのACE阻害薬もしくはARBからの切り替えで、明らかな予後改善効果があります。
エビデンス
PARADIGM-HF試験 (2014)
研究デザイン
対象:HFrEF(左室駆出率≦40%(後に35%に修正))の慢性心不全患者
比較:サクビトリルバルサルタン vs. エナラプリル(ACE阻害薬)
主要評価項目:心血管死+心不全による入院の複合エンドポイント
結果
サクビトリルバルサルタン群の有意な優越性
心血管死または心不全による入院のリスクを 20%低下(HR 0.80, p<0.001)
心血管死 20%減少(HR 0.80, p<0.001)
心不全による入院 21%減少(HR 0.79, p<0.001)
全死亡率 16%減少(HR 0.84, p<0.001)
意義:この試験の結果を受けて、サクビトリルバルサルタンは ACE阻害薬よりも優れたHFrEFの標準治療 として推奨されるようになった。
PIONEER-HF試験 (2019)
研究デザイン
対象:急性脱compensated HFrEFで入院した患者
比較:サクビトリルバルサルタン vs. エナラプリル
主要評価項目:NT-proBNP(心不全バイオマーカー)の変化
結果
NT-proBNPが4週間でより大きく減少
サクビトリルバルサルタン群:47%減少
エナラプリル群:25%減少
p<0.001
心血管イベントの抑制
サクビトリルバルサルタン群の方が、心不全悪化による再入院や死亡が少なかった。
意義:急性心不全入院中からのARNI導入の有効性 を示唆、急性期からのARNI導入がより早期の予後改善につながる可能性を示した。
TRANSITION試験 (2018)
研究デザイン
対象:HFrEFで入院し、安定化した患者
比較:入院中 vs. 退院後にサクビトリルバルサルタンを開始
主要評価項目:治療継続率
結果
入院中開始と退院後開始で同程度の治療継続率
入院中開始群:86.4%
退院後開始群:89.6%
→ 安全に入院中からARNIを導入可能
意義:退院前からのARNI導入が可能であることを確認、早期導入の安全性を支持
PARAGON-HF試験 (2019)
研究デザイン
対象:HFpEF(左室駆出率≧45%)の心不全患者
比較:サクビトリルバルサルタン vs. バルサルタン
主要評価項目:心血管死+心不全による入院の複合エンドポイント
結果
主要評価項目の差は統計的に有意ではなかった(HR 0.87, p=0.06)
ただし、LVEFが低めの患者(45–57%)では有意に有効
女性では明確な利益
意義:HFpEFに対するARNIの有効性は部分的(特定のサブグループでは有効)、HFpEFの標準治療としては確立されず、慎重な適応が必要
意義:退院前からのARNI導入が可能であることを確認、早期導入の安全性を支持
LIFE試験 (2021)
研究デザイン
対象:HFrEFで腎機能低下を伴う患者(eGFR 20–60)
比較:サクビトリルバルサルタン vs. バルサルタン
主要評価項目:NT-proBNP変化
結果
サクビトリルバルサルタン群の方がNT-proBNPの低下が大きい
腎機能の低下はバルサルタン群と同程度
意義:腎機能低下患者にもARNIは適応可能、腎機能悪化のリスクはACEI/ARBと同程度
まとめ
| 試験名 | 対象 | 比較 | 結果・意義 |
|---|---|---|---|
| PARADIGM-HF (2014) | HFrEF | エナラプリル vs. ARNI | 心血管死・入院リスクを大幅低下、標準治療へ |
| PIONEER-HF (2019) | 急性心不全(HFrEF) | エナラプリル vs. ARNI | 急性期からのARNI導入でNT-proBNP低下 |
| TRANSITION (2018) | HFrEF(入院中・退院後) | 退院前 vs. 退院後開始 | 入院中導入も安全 |
| PARAGON-HF (2019) | HFpEF | バルサルタン vs. ARNI | LVEF低めや女性では有効性示唆 |
| LIFE (2021) | HFrEF+腎機能低下 | バルサルタン vs. ARNI | 腎機能低下例でもARNI使用可能 |
臨床的インパクト
-
HFrEFではARNIがACEI/ARBより優れる(PARADIGM-HF)
-
急性期からのARNI導入が有効(PIONEER-HF, TRANSITION)
-
HFpEFでは一部の患者で有効性が示唆(PARAGON-HF)
-
腎機能低下患者でも使用可能(LIFE)
これらのエビデンスにより、HFrEF患者ではARNIが標準治療とされ、HFpEFや腎機能低下患者への適応も広がりつつあります。
SGLT2阻害薬
糖尿病治療薬として開発されたSGLT2阻害薬ですが、ダパグリフロジン(フォシーガ)とエンパグリフロジン(ジャディアンス)には
① 心不全再入院を減らす効果 ② 心血管死亡(心筋梗塞などによる死亡)を減らす効果が大規模研究によって認められています。糖尿病の有無にかかわらず、心不全治療薬として使用されるようになってきています。
sGC刺激薬
ベルイシグアトはGTPからcGMPを産生する可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)を刺激する薬剤です。cGMPはPKGを介してさまざまな血管・心筋保護効果をもたらすと考えられています。ベルイシグアトの有効性を見た大規模臨床研究は、腎機能など他の薬剤の大規模臨床研究より重症の症例がエントリーされていたことより、重症心不全での予後改善効果が期待されています。一方、血圧低下に注意する必要があり、血圧にて容量設定がなされています。
1. VICTORIA試験
2020年に発表されたVICTORIA試験は、ベルイシグアトの有効性と安全性を評価した大規模な第3相無作為化二重盲検プラセボ対照試験です。 この試験には、慢性心不全(NYHAクラスII~IV)で左室駆出率が45%未満の患者5,050名が参加し、ベルイシグアト(目標用量10 mg/日)またはプラセボが投与されました。主要評価項目は、心血管死または心不全による初回入院の複合エンドポイントでした。
結果:
-
ベルイシグアト群では、主要評価項目のイベント発生率が35.5%(897/2,526人)であったのに対し、プラセボ群では38.5%(972/2,524人)でした。ハザード比は0.90(95%信頼区間 [CI]:0.82~0.98、P=0.02)であり、統計的に有意なリスク低減が示されました。
-
心不全による入院は、ベルイシグアト群で27.4%、プラセボ群で29.6%と、ベルイシグアト群で減少傾向が見られました(ハザード比:0.90、95% CI:0.81~1.00)。
-
心血管死の発生率は、ベルイシグアト群で16.4%、プラセボ群で17.5%であり、ハザード比は0.93(95% CI:0.81~1.06)で、統計的有意差は認められませんでした。
2. メタアナリシス
2023年に発表されたメタアナリシスでは、ベルイシグアトの心不全に対する有効性を評価するため、複数の無作為化比較試験のデータが統合されました。 この解析では、ベルイシグアトは心血管死または心不全による入院の複合リスクを有意に低下させることが示されました(オッズ比:0.87、95% CI:0.78~0.97、P=0.02)。しかし、個別の評価項目である心不全による入院、心血管死、全死亡率に関しては、統計的有意差は認められませんでした。
結論:
これらのエビデンスから、ベルイシグアトは慢性心不全(HFrEF)患者において、心血管死または心不全による入院のリスクを低減する可能性が示されています。ただし、個々の評価項目に関してはさらなる研究が必要であり、臨床的な有用性を明確にするためには追加の試験が求められます。
HCNチャネル阻害薬
イバブラジンはHCNチャネル(主にHCN4チャネル)を阻害することでIf:過分極活性化陽イオン電流を抑制し、拡張期脱分極相における活動電位の立ち上がりを遅らせることで、心拍数を減少させ、心臓の負担を軽減する効果を現します。心不全患者の心拍数を抑制することで予後が改善する。これが、イバブラジンの誕生の契機です。イバブラジンは、β遮断薬の導入や増量が困難な低心機能症例に対して、心拍数を減少させる目的で導入されます。イバブラジンは、特に心拍数75/分以上の洞調律患者に対して、有用と思われます。イバブラジンは1回2.5mg、1日2回から導入を開始し、徐々に増量させていきます。
1. SHIFT試験
SHIFT試験は、慢性HFrEF患者におけるイバブラジンの有効性と安全性を評価した大規模な無作為化二重盲検プラセボ対照試験です。この試験には6,505名の患者が参加し、イバブラジンまたはプラセボが投与されました。主要評価項目は、心血管死または心不全による入院の複合エンドポイントでした。
結果:
-
イバブラジン群では、主要評価項目のリスクが18%低下しました(ハザード比0.82、95%信頼区間0.75–0.90、p<0.0001)。
-
心不全による入院は26%減少し(p<0.0001)、心不全による死亡は26%減少しました(p=0.014)。
-
全死亡率や心血管死に関しては有意な差は認められませんでした。
2. メタアナリシス(2017年)
2017年に発表されたメタアナリシスでは、イバブラジンとβ遮断薬の併用療法とβ遮断薬単独療法を比較し、HFrEF患者における有効性を評価しました。
結果:
-
イバブラジン併用群では、心拍数の有意な低下が認められました(平均差6.14拍/分の減少、p<0.001)。
-
心不全再入院と心血管死の複合エンドポイントに関しては、イバブラジン併用群で改善傾向が見られましたが、統計的有意差はありませんでした(リスク比0.93、p=0.354)。
-
全死亡率、心血管死亡率、心不全による入院に関しても有意な差は認められませんでした。
3. メタアナリシス(2021年)
2021年のメタアナリシスでは、慢性HFrEF患者におけるイバブラジンの心機能への影響が評価されました。
結果:
-
イバブラジン投与群では、左室駆出率(LVEF)の有意な改善が認められました(平均差3.89%、p<0.001)。
-
左室拡張末期径(LVEDD)、左室収縮末期径(LVESD)、左室拡張末期容積(LVEDV)、左室収縮末期容積(LVESV)などの心エコー指標も改善が見られました。
4. メタアナリシス(2024年)
2024年のメタアナリシスでは、急性心不全患者におけるイバブラジンの有効性と安全性が評価されました。
結果:
-
イバブラジンは心拍数、BNPおよびNT-proBNPレベルを有意に低下させ、左室駆出率(EF)を有意に改善しました。
-
6分間歩行距離、全死亡率、心原性死亡率、再入院率、徐脈、心房細動の発生率に関しては、イバブラジン群と対照群で有意な差は認められませんでした。
結論:
これらのエビデンスから、イバブラジンはHFrEF患者において心拍数の低下、左室駆出率の改善、心不全による入院リスクの低減などの有益な効果を示しています。特に心拍数が高い患者において、その効果が顕著である可能性があります。ただし、全死亡率や心血管死に関しては一貫した有意差が示されていないため、患者個々の状態を考慮した上での適切な適応が重要です。