DPP-4阻害薬と炎症性腸疾患との関連
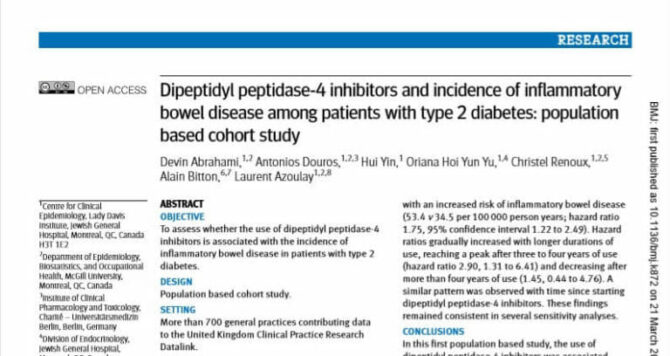
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and incidence of inflammatory bowel disease among patients with type 2 diabetes: population based cohort study.
Abrahami D, Douros A, Yin H, Yu OHY, Renoux C, Bitton A, Azoulay L.
BMJ. 2018 Mar 21;360:k872.
British Medical Journal誌に掲載された、DPP-4阻害薬と炎症性腸疾患との関連についての論文です。
DPP-4阻害薬はインクレチン関連薬と呼ばれる薬の1つで、DPP-4というインクレチンを分解する酵素を妨害することにより、結果として血糖降下作用のあるインクレチンの血液濃度を高める作用のある薬です。
血糖降下作用はマイルドで低血糖を起こしにくいという利点があり、2型糖尿病の治療薬として、日本では今最も多く使用されている薬だと思います。高齢者でも使用しやすいというのも利点です。
しかしながら、この薬の問題点は、DPP-4という酵素はインクレチンのみの代謝に関わっている訳ではなく、他の多くの細胞機能にも少なからず影響を与えているので、それが別個の問題を引き起こすという可能性が、完全には否定されていないということです。
そこで1つ危惧されているのは、DPP-4と難病でもある炎症性腸疾患との関連です。
動物実験においては、DPP-4阻害剤による治療が炎症性腸疾患の病勢を和らげたという報告があります。
その一方で臨床的な知見としては、炎症性腸疾患の患者さんの血液では、DPP-4の濃度が低下しており、その低下の程度と炎症の強さとの間にも関連が認められたという報告も複数存在しています。
しかし、実際の患者さんにおいて、DPP-4阻害剤の使用と炎症性腸疾患の発症リスクとの間に関連があるかどうかを検証した疫学データはこれまでに殆どありませんでした。
そこで今回の研究では、イギリスのプライマリケアのデータベースを活用してDPP-4阻害剤の2型糖尿病の患者さんに対する継続処方とその後の炎症性腸疾患の発症リスクとの関連を検証しています。18歳以上の141170名の糖尿病の患者さんのデータを解析した大規模な疫学研究です。
その結果、トータルで208件の炎症性腸疾患が診断され、年間10万人当たり37.7件という発症率になっています。
そして、このうちDPP-4阻害剤を使用している患者さんの発症率は年間10万人当たり53.4件であったのに対して、それ以外の糖尿病治療薬を使用している患者さんでは34.5件となっていて、DPP4阻害剤の使用により炎症性腸疾患の発症リスクは1.75倍(95%CI: 1.22から2.49)有意に高くなっていました。
このリスクの増加は、DPP-4阻害剤の使用期間が長いほどより高く、継続期間が4から5年で2.90倍(95%CI; 1.31 から6.41)と最も高くなり、4年以上の使用では有意な増加は認められなくなっていました。
このように、かなりばらつきはあるデータで、本当にDPP-4阻害剤が原因となって炎症性腸疾患のリスクが増加しているかどうかは、断定出来ませんが、今後より厳密な検証が必要な事項であると思いますし、DPP-4阻害剤の長期使用時には、そうしたリスクについてもじゅうぶんに留意する必要があります。
