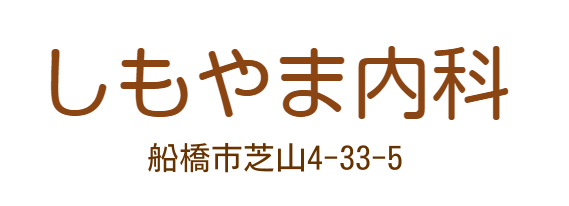🔊 このページの要点(糖尿病の運動療法)
- 運動は「量」より「安全に続く設計」が重要です。最初は“少なめ”でOK。
- 目標の目安:中強度の有酸素運動を週150分+筋トレを週2〜3回(非連日)。
- 強度は「トークテスト」で決められます(会話できる=中強度)。
- 低血糖が不安な方(インスリン・一部内服)は、運動前後の血糖確認が安全の土台です。
- 足の痛み・しびれ、胸痛、強い息切れがある時は無理をせず、相談が必要です。
🔎 運動療法を「続けて成果につなげる」ための考え方
- ① まずは安全:体調確認 → 低血糖/脱水/痛みを避ける。
- ② 次に継続:週150分は「10分×3回」でも積み上がります。
- ③ 最後に最適化:筋トレを足すと血糖と筋力の両方に効きます。
運動療法は、血糖値だけでなく、体力・筋力・気分・睡眠にも良い影響があります。とはいえ、「何を、どれくらい、どの強さで、いつやればいいの?」が一番難しいところです。
このページでは、安全に続けるための「具体的な設計」を、できるだけ分かりやすくまとめます(保険診療の外来での運動指導の考え方に沿った内容です)。
まず結論:運動の目標(目安)
- 有酸素運動:中強度で週150分を目安(週3日以上/連続2日以上空けないのが理想)。
- 筋トレ:大きい筋肉を使う運動を週2〜3回(できれば非連日)。
- 座りっぱなし対策:長時間の座位は、可能ならこまめに中断(短い立ち上がり・歩きでOK)。
※上記は国際的なガイドライン・運動指針に沿った目安です(本文末の参考文献をご参照ください)。
運動の強さ(強度)は「トークテスト」で決められます
「中強度」が分かりにくい時は、次の目安が便利です。
✅ 中強度(おすすめ)
- 息は少し上がるが会話はできる
- 「ややきつい」くらい
- 例:早歩き、軽い坂道歩行、自転車(軽〜中)
⚠ 高強度
- 会話が難しい(短い言葉しか出ない)
- 運動習慣がない方は、まず中強度から
- 心血管リスクや合併症がある方は、開始前に相談
コツは、最初の2週間は「物足りない」くらいでOKにすることです。続くほど、血糖や体力への効果は積み上がります。
続く人がやっている「週の組み立て」
週150分は、きれいに30分×5回でなくても構いません。分割して積み上げる方が続きます。
例:現実的なスタート(最初の2週間)
- 平日:10分の早歩き × 2回(通勤・買い物に組み込む)
- 週2回:椅子スクワット+かかと上げ(各10回×2セット)
- できたら上積み:休日に20〜30分の散歩
筋トレ(自宅でOK:目安10分)
- 椅子スクワット(下肢)
- 壁腕立て or ゴムバンド(上肢)
- 体幹:立位で腹圧を意識して姿勢保持(30秒×2〜3)
※関節痛や転倒が心配な方は、椅子や手すりを使うと安全です。
安全に続けるためのチェック
運動を中止して相談が必要なサイン
- 胸の痛み・圧迫感、強い動悸、冷汗
- いつもと違う強い息切れ、めまい・ふらつき
- 低血糖を疑う症状(手の震え、強い空腹感、ぼーっとする等)
- 足の傷が悪化、強い痛み・しびれの悪化
低血糖が心配な方へ(インスリン・一部の内服薬)
インスリン治療中の方や、低血糖を起こしやすい薬を使っている方では、運動前後の血糖確認が安全の土台になります(個別の調整は治療内容により異なるため外来で相談が必要です)。
- 「低血糖が怖くて運動できない」方は、運動のタイミングや強度、必要に応じた補食の工夫で改善できることがあります。
- 運動後〜夜間に低血糖が起こることもあるため、運動量が増えた日は夜間の注意も大切です。
- CGMを使用している方は、アラート設定や運動前後の変化の見方を一緒に整理します。
合併症がある方の注意(よくあるポイント)
- 足のしびれ・足病変が心配:靴ずれ・傷のチェック、低衝撃(自転車・水中歩行など)を検討。
- 目の合併症が心配:強いいきみや高強度は控えめにして、主治医と相談。
- 腎機能が気になる:脱水を避け、強度は段階的に。
- 心血管リスクが心配:まずは中強度から安全に開始。高強度の開始は相談。
セルフチェックシート(1週間)で「続く形」を作る
運動療法は“できたこと”を見える化すると続きます。1週間だけでも、実施時間・痛み・体調・(可能なら)血糖の変化を記録してみてください。
運動の不安チェック(匿名・2分)
「低血糖が怖い」「足が痛い」「強度が分からない」…そんな不安を整理できます。
- このフォームは匿名で、氏名・連絡先などの個人情報は収集しません
- 診断を行うものではありませんが、安全に運動を続けるための目安になります
- 迷いが強い方は、外来で一緒に調整できます(電話でご相談ください)
「受診した方が良い」振り返りポイント
次のどれかに当てはまる場合は、運動のやり方を外来で一緒に調整すると安全に進めやすくなります。
- 低血糖が怖くて運動できない/運動後にふらつく
- 運動で膝・腰・足が痛くなる(続けられない)
- 運動すると血糖が乱れる気がして不安
- 心臓・息切れが心配で強度が決められない
- 何をやればいいか分からない(計画が立てられない)
よくあるご質問(FAQ)
運動はいつやるのが良いですか?
筋トレは必要ですか?
運動中に気分が悪くなったら?
📚 参考文献・出典
- American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes – 2024. Diabetes Care. 2024;47(Suppl 1).(運動療法:有酸素運動150分/週、筋力トレーニング週2–3回 など)
- Colberg SR, et al. Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2016;39(11):2065–2079.(運動強度の考え方、低血糖リスク、合併症別注意点)
- American College of Sports Medicine (ACSM). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 11th ed. Wolters Kluwer; 2021.(トークテスト、自覚的運動強度、心血管リスク評価)
- 日本糖尿病学会. 糖尿病診療ガイドライン 2024. 南江堂.(日本における運動療法の基本方針、合併症への配慮)
- ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022. Exercise in children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes. 2022.(インスリン使用時の低血糖対策・遅発性低血糖の考え方)
👨⚕️ この記事の監修医師
しもやま内科 院長
- 日本内科学会 総合内科専門医
- 日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医
- 日本循環器学会 循環器専門医
- 日本老年医学会 老年病専門医・指導医
- 日本甲状腺学会 甲状腺専門医
糖尿病診療に長年携わり、生活習慣(食事・運動)と薬物療法を組み合わせて、継続しやすい治療計画を提案しています。