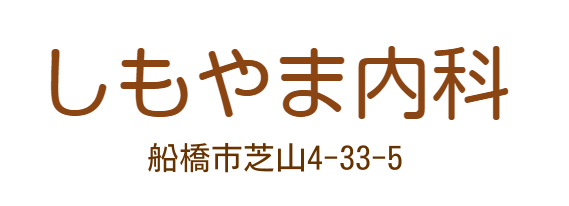心不全は、心臓のポンプ機能が弱り息切れ・むくみ・体重増加・夜間の呼吸苦などをきたす状態です。
早めの受診と、心電図・心エコー・血液検査などの評価が重要です。塩分・水分・体重管理と内服治療でコントロールします。
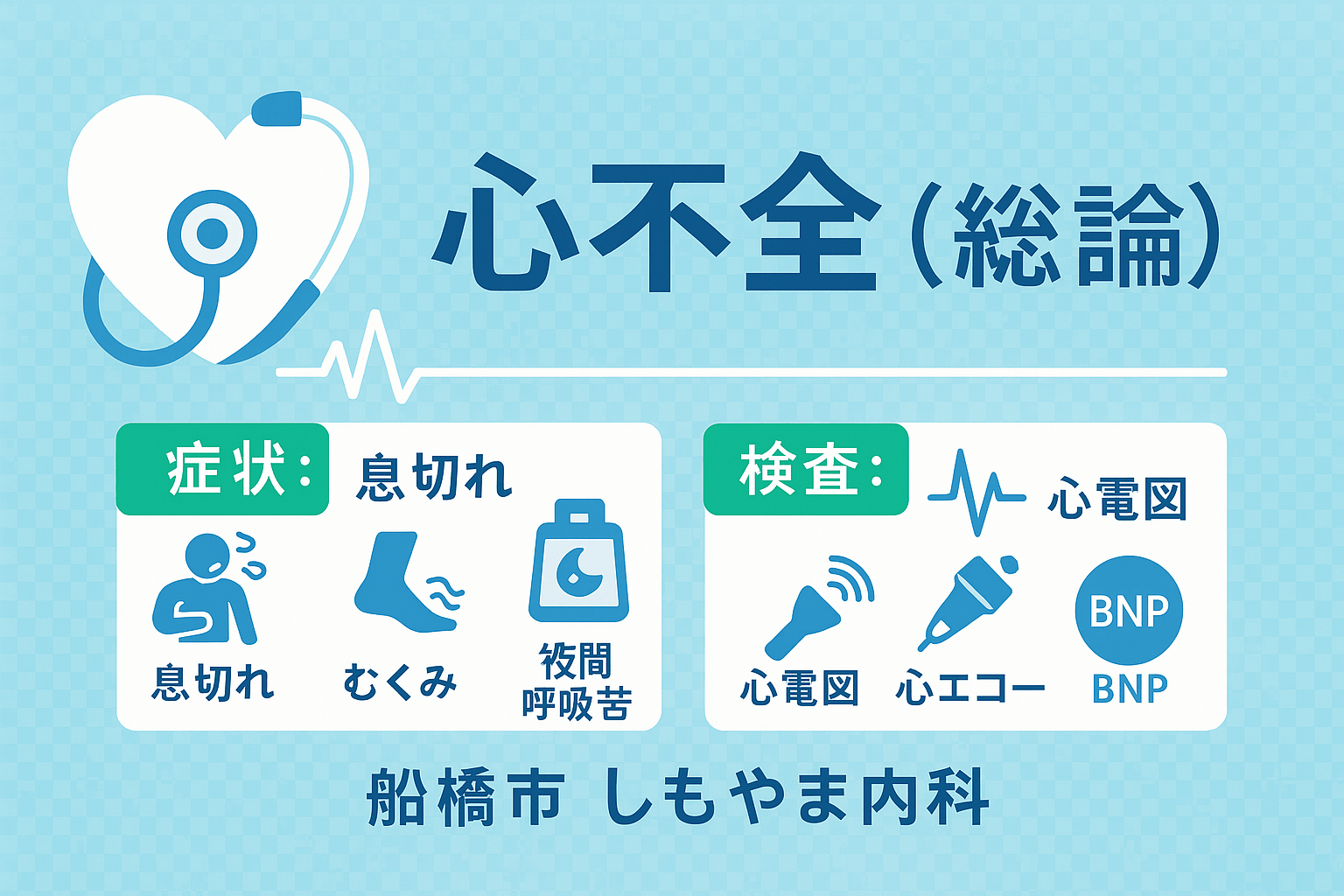
心不全は病名というより「心臓のはたらきが落ち、全身に十分な血液を送れない状態」の総称です。原因(虚血・高血圧・弁膜症・不整脈・心筋症など)やタイプ(収縮不全・拡張不全)により対応が異なりますが、息切れ・むくみ・体重急増・夜間の呼吸苦は共通のサインです。気づいた段階で受診いただくと、悪化を防げる可能性が高くなります。
このページの構成
受診の目安(危険サイン)
- 階段や平地での息切れが増えた、横になると苦しい・夜間に息苦しくて起きる
- 足のむくみ・体重が短期間に増える(例:2–3日で2kg以上)
- 動悸・胸の違和感・めまい・失神傾向
- 食欲低下、倦怠感、咳・痰が増えた
迷ったら早めの受診を:症状が軽くても、心不全の初期や再増悪のことがあります。まずは状態を評価し、必要に応じて治療を始めましょう。
当院で可能な検査
- 心電図(12誘導):不整脈・虚血の手がかり
- 心エコー:心機能(収縮・拡張)、弁膜症、心筋症の評価
- 血液検査:腎機能・電解質・BNP/NT-proBNP など
- 胸部X線(必要時):心拡大・肺うっ血
- 頸動脈エコー:動脈硬化の評価(リスク層別化)
- ホルター心電図:日常生活中の不整脈評価(必要時手配)
検査結果から、重症度や原因、今後の治療方針(内服調整、入院適応、連携病院への紹介)を判断します。
治療の流れ(外来)
- 原因とタイプを見極める:虚血・弁膜症・高血圧・不整脈・心筋症など
- 内服の最適化:利尿薬、心不全治療薬の導入・調整(腎機能・血圧・電解質をみながら少量から)
- 生活指導:塩分控えめ(目安 6g/日未満)、過度の飲水を避ける、体重・血圧・むくみの自己チェック
- 再評価:通常は2–4週間で外来フォロー、安定すれば間隔を延ばします
- 専門治療連携:弁膜症やデバイス適応・虚血再血行化が必要な場合は、地域連携病院へ速やかにご紹介
自己管理のコア:毎朝の体重測定(同じ条件で)、血圧記録、むくみ・息切れの変化をメモし、受診時に共有してください。
🧪 心不全に対する新しい治療薬(要約)
心不全の治療ガイドラインは年々アップデートされています。基盤治療(ARNI/ACEi/ARB・β遮断薬・MRA・SGLT2i)に加え、増悪リスクや併存症に応じて新規・拡張治療を検討します。
適応・保険収載・用量は変更され得るため、最新情報は下記の更新記事をご確認ください。
- ARNI(サクビトリル/バルサルタン):ACE/ARBからの置換を含めて適応に応じて検討。導入時は血圧・腎機能・Kを厳密にモニタリング(ACEから切替時は一定の休薬間隔が必要)。
- SGLT2阻害薬:糖尿病の有無を問わず心不全転帰改善に寄与。体液量・腎機能・尿路/外陰部感染に留意しつつ導入。
- 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬(例:ベルイシグアト等):最近の増悪歴があるHFrEFで再増悪抑制を狙う選択肢。低血圧に注意。
- 静注鉄補充(鉄欠乏合併):フェリチン低値や機能的鉄欠乏がある症例で運動耐容能や症状の改善を期待。鉄代謝指標の定期評価が前提。
- 心拍数制御薬(イバブラジン等):洞調律でHR高値が持続しβ遮断薬最適化後も症状が残る場合に検討。
- 急性増悪期の併用(入院治療):アセタゾラミド等の利尿補助など、入院下で適応と反応性を確認。
安全性・運用上のポイント
- 導入は少量から開始し、血圧・腎機能・電解質・心拍を見ながら段階的に最適化。
- 多剤併用時は低血圧・腎前性悪化・高K血症・脱水に特に注意。
- 高齢者・腎機能低下・低体重では初期用量保守的+増量ゆっくりを原則に。
- 自己判断での中止・増量は厳禁。症状変化時は早めの受診を。
要約:基盤治療を土台に、適応に応じてARNI・SGLT2i・再増悪抑制薬・静注鉄などを追加。導入時は血圧・腎機能・K・体液量を厳密に確認します。
再発予防・日常生活のポイント
- 体重・血圧・症状の「トリガー」を把握:増悪の早期サインを掴む
- 塩分6g/日未満を目標(加工食品・外食に注意)
- 指示がある場合は飲水目安を遵守(腎機能・季節で調整)
- 内服は中断しない:副作用や不安があれば自己判断せずご相談を
- ワクチン(インフル・肺炎球菌など)や感染対策で悪化予防
- 軽い運動は主治医と相談のうえ段階的に再開
関連ページ
よくある質問(FAQ)
心不全は治りますか?
体重が急に増えたらどうすれば?
どのくらいの間隔で通院が必要ですか?
旅行や運動はできますか?
症状評価から検査、内服調整、生活指導まで丁寧に対応します。必要時は連携病院へ迅速にご紹介します。
👨⚕️ この記事の監修医師
しもやま内科 院長/循環器専門医・総合内科専門医 ほか
地域での心不全診療に長年従事し、検査から生活指導まで一貫してサポートしています。