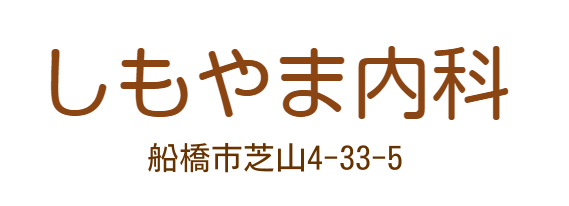亜鉛は味覚・免疫・皮膚や髪の健康に関わる必須ミネラルです。気づきにくい不調の背景に亜鉛不足が隠れていることがあります。食事での摂り方とサプリの注意点を、しもやま内科が分かりやすく解説します(ご相談は 047-467-5500)。
亜鉛は私たちの体内で幅広く働いている欠かせないミネラルです。味覚、免疫、皮膚や髪の健康、細胞の修復や再生などに関与しており、不足すると様々な不調が現れます。
ところが、亜鉛不足は初期には自覚しにくく、知らず知らずのうちに「低下症」の状態に陥ることもあります。このページでは、亜鉛低下症のリスクが高い方が意識すべき食事の工夫と、サプリメント活用の注意点をわかりやすく解説します。
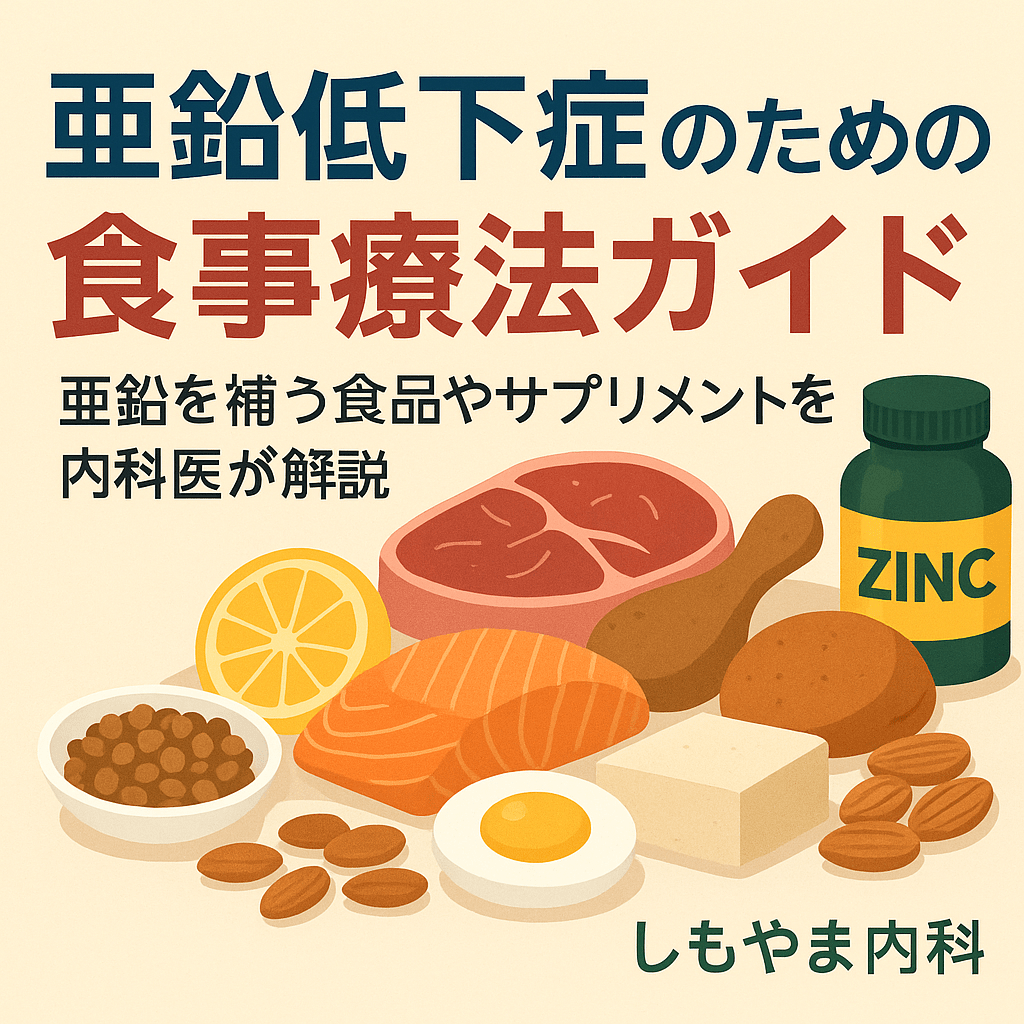
亜鉛不足になりやすいのはどんな人?
次のような方は特に亜鉛不足に注意が必要です:
- 高齢者(食事量・吸収力が低下しやすい)
- 妊娠中・授乳中の方(必要量が増える)
- 成長期の子ども・若年層(成長に多く使われる)
- 胃腸疾患のある方(吸収不良のリスク)
- 糖尿病のある方(尿中への排泄増加)
- 過度な飲酒をされる方
- 偏食・極端なダイエットをされている方
亜鉛不足がもたらす影響
- 免疫低下(風邪をひきやすい、治りにくい)
- 味覚異常(食欲減退につながる)
- 皮膚トラブル(湿疹・かゆみが出やすい)
- 脱毛・薄毛の進行
- 創傷治癒の遅れ
気になる症状が複数あてはまる場合は、早めの医師相談をおすすめします。
亜鉛を効率よく摂取する食事の工夫
成人男性は約10mg、女性は約8mg/日の摂取が目安とされます。
食事の組み立て例(シンプル)
| 食事の場面 | 亜鉛を取り入れる工夫例 |
|---|---|
| 朝食 | 胚芽米ごはん+納豆+卵 |
| 昼食 | 牛肉入り野菜炒め+小鉢に豆腐 |
| 夕食 | 魚介(牡蠣、うなぎなど)+野菜たっぷりスープ |
ポイント
- 魚介・肉・卵・豆類など、動物性たんぱく+植物性食品を組み合わせる
- 発酵食品(納豆、味噌など)を活用する
サプリメント活用は慎重に
食事だけで十分摂取が難しい場合、サプリメントの活用も選択肢になります。ただし、製品の品質や用量には差があるため注意が必要です。
- 形態と品質:吸収の良い形態(例:グルコン酸亜鉛、酵母由来など)を選ぶ
- 過剰摂取に注意:長期の高用量は鉄や銅の吸収を妨げることがある
- 併用注意:他サプリ・薬との相互作用は事前に確認
当院の考え方
サプリメントを選ぶ際は医師・薬剤師に相談のうえ、信頼できる製品を適切な量で使用することが重要です。
「とりあえずネットで安いものを買う」はおすすめできません。
医師への相談が必要なケース
以下のような場合は、自己判断でサプリを追加する前に必ず医師へ相談してください:
- 持病(腎疾患・肝疾患・糖尿病など)がある
- 妊娠中・授乳中
- 他のサプリや薬を多用している
- 明らかな皮膚トラブル・味覚異常・脱毛などの症状がある
まとめ
- 亜鉛は不足しやすく、気づきにくい体調不良の背景となることがある
- まずは食事からの摂取を基本に、必要に応じてサプリを検討
- サプリは品質・用量を重視し、医師と相談して安全に活用
👨⚕️ この記事の監修医師
しもやま内科 院長
日本内科学会 総合内科専門医/日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医/日本循環器学会 循環器専門医/日本老年医学会 老年病専門医・指導医/日本甲状腺学会 甲状腺専門医
糖尿病、甲状腺、副腎など内分泌疾患の診療に長年従事し、地域密着型の総合内科医として診療を行っています。栄養・食事療法のサポートにも力を入れています。
栄養・食事療法に関する関連記事