【要点まとめ】
- 甲状腺炎には急性化膿性・亜急性・無痛性(サイレント)・産後などのタイプがあり、痛みの有無・発熱・採血/エコー所見が手掛かりです。
- 多くは中毒(ホルモン漏出)→低下→回復の時相をたどります(全例ではありません)。
- 痛みが強い亜急性甲状腺炎はNSAIDsで不十分なら低用量ステロイドを検討します。
- 授乳・妊娠では、薬剤選択や治療タイミングに配慮します(β遮断薬・ステロイド・甲状腺ホルモン補充など)。
このページは、甲状腺炎の全体像(タイプ別の特徴と診療のポイント)をまとめた分岐ハブです。個別ページ(詳細解説)へのリンクも設置しています。
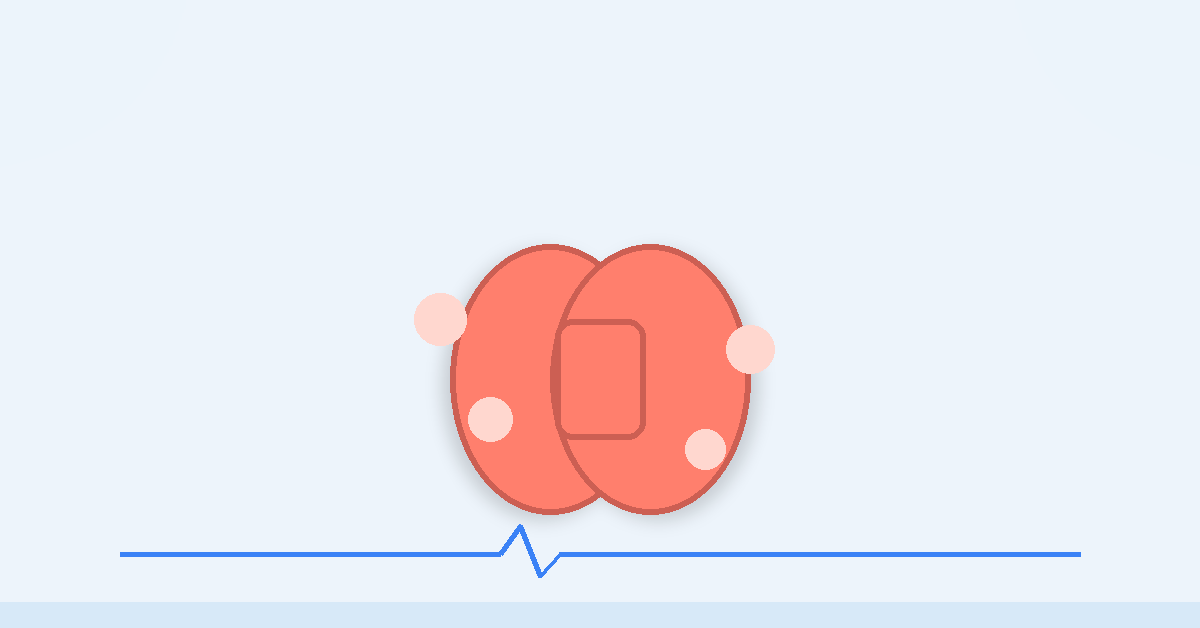
甲状腺炎のタイプと特徴
- 急性化膿性甲状腺炎:細菌感染が多く、発熱・局所の強い痛み・発赤/腫脹。白血球↑、CRP↑。
▶ 抗菌薬、切開排膿(膿瘍形成時)などを検討。甲状腺機能異常は軽いことが多い。 - 亜急性甲状腺炎(de Quervain):強い前頸部痛、発熱、赤沈/CRP↑、甲状腺中毒相→低下相→回復相が典型。
▶ まずNSAIDs、反応不良や重症例はプレドニゾロンなど低用量から漸減。 - 無痛性(サイレント)甲状腺炎:痛みなし。自己免疫関与(TPOAbなど陽性あり)。
▶ 中毒相はβ遮断薬で対症、低下相は必要に応じレボチロキシン補充。 - 産後甲状腺炎:出産後1年以内。無痛性と同系統で、中毒→低下→回復の順。
▶ 授乳を考慮しつつ対症療法。低下相が長引く場合は補充治療を検討。
時相(中毒→低下→回復)の考え方
炎症で濾胞から貯蔵ホルモンが漏出すると一過性の甲状腺中毒相になります。貯蔵が尽き、合成能も落ちると甲状腺機能低下相へ移行し、炎症が鎮まれば回復相に向かいます。
注意点:全員が教科書どおりの経過をとるわけではなく、各相の程度・期間は個人差があります。
再発率・経過の目安
- 亜急性甲状腺炎:再発は一定割合で起こりえます(初回発症から数か月〜数年)。早期に痛みが再燃する「漸減中のぶり返し」にも注意。
- 無痛性/産後甲状腺炎:産後は再発しやすい素地(自己免疫背景)。低下相が長引く場合は長期補充が必要なことも。
当院では、定期採血(TSH/FT4/FT3)+甲状腺エコーで経過を見ながら、投薬量や漸減速度を調整します。
鎮痛薬・ステロイドの適応(実践の勘所)
- NSAIDs(ロキソプロフェン等):多くの亜急性例はまずNSAIDsで疼痛・炎症の改善を狙います。胃障害・腎機能に注意。
- ステロイド:NSAIDsで不十分、痛みが強い/生活に支障、炎症反応が高い場合に検討。
例)プレドニゾロンの低用量開始→数日で痛み・発熱が鎮まれば緩やかに漸減。再燃時は一段戻す。 - β遮断薬:中毒相の動悸/振戦/不安感の緩和に有用(授乳期は薬剤選択・用量を個別判断)。
- 抗甲状腺薬:「漏出型」甲状腺炎では基本的に不要(合成抑制の対象ではない)。鑑別上、バセドウ病が疑わしければ別判断。
授乳・妊娠での注意点
- 授乳中:アセトアミノフェンは概ね安全域内。NSAIDsやβ遮断薬、ステロイドは薬剤ごとに授乳適合性が異なるため個別に調整します。
▶ 詳細は 授乳期に使える甲状腺薬の安全性(院内ガイド) をご参照ください。 - 妊娠中:疼痛コントロールは週数・背景により慎重に選択。中毒相はβ遮断薬の選択と期間に配慮。低下相は母体・胎児のため適切に補充。
薬の可否は週数・体質・合併症で変わるため、自己判断での中止/再開は避け、必ず医師とご相談ください。
診断に用いる検査
- 採血:TSH、FT4/FT3、炎症反応(CRP/赤沈)、サイログロブリン、自己抗体(TPOAb/TgAbなど)
- 甲状腺エコー:腫大、低エコー域、血流パターン(漏出型は血流低下〜正常、バセドウはびまん性血流増加)
- 核医学:必要時にアイソトープ取り込み(漏出型は低下)
各タイプの詳細解説(分岐)
- ▶ 亜急性甲状腺炎(痛みが強いタイプ)
- ▶ 無痛性(サイレント)甲状腺炎
- ▶ 産後甲状腺炎(出産後〜12か月以内)
- ▶ 急性化膿性甲状腺炎(感染性)
👨⚕️ この記事の監修医師
しもやま内科 院長/総合内科専門医・糖尿病専門医・循環器専門医・甲状腺専門医
下山 立志(しもやま たつし)
甲状腺エコー・採血を組み合わせ、妊娠/授乳も考慮した安全な治療をご提案します。
