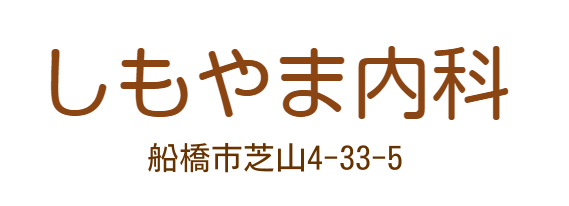小児の甲状腺結節はエコーでの形態評価が要です。低エコー・微小石灰化・境界不整などの所見がある場合は穿刺吸引細胞診(FNAC)を検討。異常が乏しければ経過観察で十分なこともあります。
学校健診や家族の気づきで発見される甲状腺結節は、小児ではサイズだけでは判断しないことが重要です。超音波(エコー)で、形態・内部性状・血流・頸部リンパ節を含めて総合評価し、必要に応じ穿刺吸引細胞診(FNAC)や追加検査を検討します。
1. エコーで見るポイント(良悪性リスクの手掛かり)
- 内部エコー:低エコー、微細・粗大石灰化、嚢胞成分の割合
- 形状・境界:境界不整、前後径>左右径(taller-than-wide)
- 血流:内部血流の増加パターン
- 周囲所見:頸部リンパ節腫大(皮質肥厚・門の消失・石灰化 など)
※ 小児は結節自体が比較的まれでも、怪しい所見の有無で次の一手を決めます。単純な大きさだけで判断しません。
2. 経過観察の間隔(例)
- 低リスク所見:6〜12か月ごとにエコーで経過観察(サイズ・内部性状・リンパ節)。
- 中等度リスク:3〜6か月間隔で再評価。変化があればFNACを検討。
- 高リスク所見:早期にFNACまたは専門施設へ紹介。
3. 穿刺吸引細胞診(FNAC)が必要になる場面
- 高リスクエコー所見がある
- リンパ節の疑わしい所見を伴う
- 増大傾向が明らか(短期間での体積増)
FNACは局所麻酔下で細い針を用い、超音波ガイドで細胞を採取します。多くは当日歩行・帰宅可能です。結果により、経過観察・再穿刺・手術検討を判断します。
4. 採血・追加検査の位置づけ
- 甲状腺機能:TSH/FT4(±FT3)で機能異常の有無を確認。
- 自己抗体:橋本病の合併評価(抗TPO/抗Tg)。
- 必要時:CT/MRI(気道偏位・後面伸展などの解剖評価)、細胞診結果に応じて遺伝子関連検査を検討(専門施設と連携)。
5. 学校生活・運動の目安
- 結節そのものは多くが運動制限不要。ただし息苦しさ・嚥下障害・痛みがある場合は活動を一時調整。
- FNAC当日は激しい運動・水泳を控え、翌日以降に段階的再開。
- 甲状腺機能異常が伴う場合は、病勢に合わせて強度を調整。
6. 受診・連絡の目安
- 短期間で急に大きくなる、痛み・急な嗄声が出現
- 呼吸しづらい、嚥下困難、首の左右差が顕著
- 学校生活に支障が出ている、保護者が強い不安を感じる
👨⚕️ 執筆・監修
下山 立志(しもやま たつし)
院長/
しもやま内科
資格:日本甲状腺学会 甲状腺専門医・日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・日本内科学会 総合内科専門医 ほか
院長/
しもやま内科
資格:日本甲状腺学会 甲状腺専門医・日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・日本内科学会 総合内科専門医 ほか
最終更新日:2025-10-19(JST)
本ページは一般的な解説です。穿刺適応や運動制限は個別のエコー所見・症状・検査結果で判断します。最終判断は担当医の指示に従ってください。