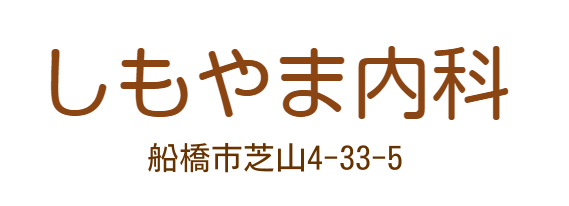「体重減少・動悸・手のふるえ・多汗」「集中力低下や成績低下」「脈が速い」「首の腫れ」が続くときは、小児基準でのTSH/FT4(±FT3)とエコーが早期診断に有用。治療は抗甲状腺薬が基本で、学校生活は病勢に応じて強度調整を。
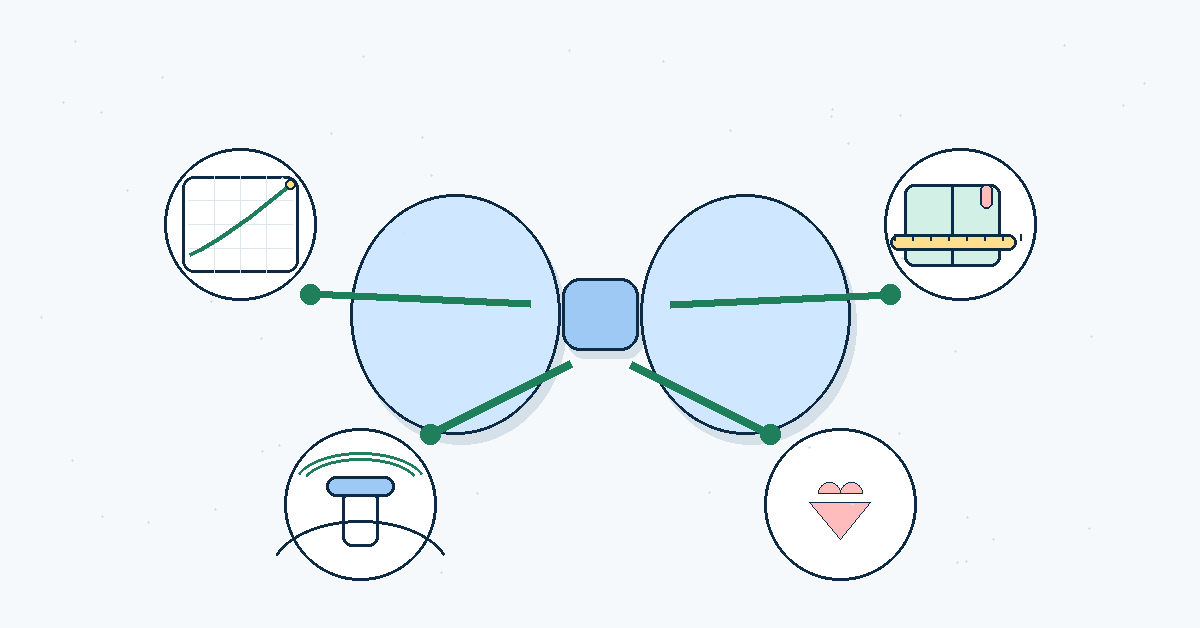
小児・思春期のバセドウ病は、体重や学業・部活のパフォーマンスに影響しやすいのが特徴です。成人と同じ症状でも、成長・発達の観点を踏まえた評価が欠かせません。当院では小児年齢の基準範囲での採血(TSH/FT4[±FT3])と甲状腺エコーを軸に、病勢・副作用リスク・学校生活を総合して治療計画を立てます。
1. 症状の見分け方(家庭で気づきやすいサイン)
- 全身:体重減少/食欲増加、だるさ、発汗過多、暑がり、下痢気味、睡眠障害
- 循環:動悸、脈が速い(安静時でも)、スマートウォッチの高心拍通知
- 神経・精神:手のふるえ、いらいら、集中困難、成績や部活のパフォーマンス低下
- 頸部:首の腫れ(びまん性甲状腺腫大)、嚥下違和感
- 眼:眼瞼後退や違和感(眼症の可能性)
※ 高熱・激しい動悸、強い脱水、意識障害などは緊急の受診対象です。
2. 検査のポイント(小児基準で判断)
- 採血:TSH低値とFT4高値(±FT3高値)を確認。必要に応じてTRAb/TSIなど自己抗体、肝機能・血算。
- エコー:びまん性腫大、血流増加(カラー)、結節の有無を評価。
- 心電図:頻脈・不整の評価。スポーツ可否の判断材料に。
- 成長発達:身長・体重曲線、初経/月経状況、学業・生活への影響を総合評価。
3. 治療:抗甲状腺薬が基本、β遮断薬を併用
- 抗甲状腺薬(MMI/PTU): 小児は原則メチマゾール(MMI)を第一選択。
副作用:発疹・関節痛・肝機能異常・無顆粒球症(発熱・咽頭痛が出たら服用中止し連絡)。 - β遮断薬: 動悸・振戦・不安の軽減に短期併用。心疾患・喘息の既往は要確認。
- ヨウ素摂取: 海藻・サプリは過量に注意(病勢評価に影響)。食事はバランス優先で過度制限は不要。
- RAI/手術: 小児では原則薬物治療が第一。無効や重篤副作用・強い増悪例では専門施設と連携し、RAIや手術を検討。
用量・増減は医師指示に従い、自己調整は不可。服薬アドヒアランス向上に家族の伴走が有効です。
4. フォローアップ:間隔と目安
- 初期〜不安定期:2〜4週ごとに診察・採血で用量調整。
- 安定期:6〜12週ごと。成長・学校行事に合わせて微調整。
- 副作用サイン:発熱・咽頭痛(無顆粒球症疑い)、発疹、黄疸/濃尿(肝障害)、著しい倦怠感は即連絡。
5. 学校・部活との両立
- 体育・部活:頻脈・熱中症リスクがあるため、病勢が落ち着くまで強度を調整。屋外・高温環境ではこまめに水分補給。
- 試験・受験:集中困難・不眠がある時期は治療優先で計画。学校側に通院・内服・配慮事項を共有。
- 生活:十分な睡眠・規則的な食事。カフェイン/エナジードリンクの過量を避ける。
6. 眼の症状が強いとき(甲状腺眼症の併発)
眼の痛み、視力低下、色の見え方の低下、視野異常などは緊急評価が必要です。眼の乾燥には点眼・夜間眼軟膏、就寝時の保護などを併用し、必要に応じ専門施設と連携して治療(ステロイド・放射線・手術)を検討します。
7. 受診の目安
- 発熱・咽頭痛(抗甲状腺薬内服中)
- 強い動悸、息切れ、めまい、脱水
- 著しい体重減少、食思不振、日常生活困難
- 視力・色覚・視野の異常や急な眼の痛み
👨⚕️ 執筆・監修
下山 立志(しもやま たつし)
院長/
しもやま内科
資格:日本甲状腺学会 甲状腺専門医・日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・日本内科学会 総合内科専門医 ほか
院長/
しもやま内科
資格:日本甲状腺学会 甲状腺専門医・日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・日本内科学会 総合内科専門医 ほか
最終更新日:2025-10-19(JST)
本ページは一般的な解説です。用量や通院間隔は年齢・病勢・副作用リスクで個別に決まります。最終判断は担当医の説明書に従ってください。